| 「施設見学をして学んだ事」 | 1年 田中 千佳 | |
| 私は、この学校に入学して初めて見学に行かせて頂いたのは、京急線の雑色駅から徒歩7分程の「特別養護老人ホーム大田翔裕園」と「老人保健施設大田ナーシングホーム」でした。 今年の4月から開設されたという事で、とても綺麗な建物でした。なるべく外から見るとマンションのように見えるように建設されているという事を聞いて、確かに外から見たら「老人ホーム」とはあまり分からないなあと思いました。施設を設計してから建物が完成するまで約4年間かかり、建設費は27億円と聞いて、かなり驚きましたが、やはり作りはすごくて、床は転んでもケガをしにくい床や、手すりもどんな人でも握りやすい裏にくぼみがあるもの、居室は和風で障子がついていたり、ベッドか布団を選べるという事で利用者さん中心でとても良い施設だと思いました。 「特別養護老人ホーム」と「老人保健施設」を両方見学させて頂き、やはり「老人保健施設」の方がレクリエーション等を活発に行っていて、元気な方が多いという事が分かりました。 最後に私達は、「特別養護老人ホーム」で七夕に近いので「七夕さま」とお年寄りの方が分かる「故郷」を歌わせて頂くと、利用者さんも一緒に歌ってくれて、喜んで下さり、とてもうれしかったです。お年寄りの方は外から来た人でも、やさしく受け入れてくれる事が分かり、うれしく思いました。 施設の方も、介護のやりがいは、レクリエーションの時、利用者の方がとてもいつもと違う良い表情を見せて下さると言っていましたが、それがとても良く分かりました。 施設見学に行って、介護福祉士になるためには技術だけが仕事ではないという事を学んだので心も磨いてがんばっていこうと思いました。 |
   |
|
| 「様々な福祉機器を見て」 | 1年 佐藤 里美 | |
| 今回国際福祉機器展では私が障害者、又その介護者や家族の立場になった時買ってみたい、使ってみたいと思う所はどこだろうと考えながら、見学に望んでみました。しかし、あまりの種類の数に圧倒され目移りするばかりで視点がなかなか定まりませんでした。そんな時、車椅子に乗った障害者が沢山この機器展に来ている事に気付きました。そして、その車椅子に目を向けてみると持ち主によって模様や絵が異なり、持ち主の個性が現れていました。思えば、人は何かを購入する時にデザインに中心をおき、楽しむのでしょう。そこで、私は、さまざまな福祉用具のデザインを見てみました。車椅子にはカラフルな色があり、アームレストの部分など木の素材や布の素材が使われており、食器においても思っていた以上に色やデザインがあり楽しんで見る事が出来ました。 次に私が気付いた事はさまざまな福祉用具の機能性でした。食器や車椅子の機能の違いについては授業で少し知っていましたが、今回の見学ではkokuyoから沢山の文房具用品の福祉用具とその機能性を知りとても驚き、感動してしまいました。特に、片手使用の人のための用具がよく考えられておりファイルはワンタッチで開けられ、ホチキスは置いて閉じる事が出来るよう安定されていました。またハサミの開閉がスムーズにいくようにバネによって自動的に開くようになっていたり、持ちやすいようにカーブの曲がり具合など変えてあったりと工夫がされていました。このように、文房具においても工夫された用具が沢山ある事を知り他の福祉機器の機能についても見てみることにしました。その結果からその用具によってもいろいろな工夫がされており、この用具があったら便利だろうと思うものがいろいろありました。 そして機能性については、特に私の祖母が足が不自由なため、それにあった用品に目を向けてみました。立位のしやすい用具においては価格は10万辺りのものが多く購入は難しいですが自動的に椅子の座面が上がり立位がしやすい椅子やトイレの便座があり惹かれました。また、座位や寝ている状態の多い祖母に床ずれ予防や座りやすさや寝やすさにおいて見てみるとクッション製の優れたものがいくつかあり、いろいろな素材を使用してその機能性を高めているようでした。また、靴の履きやすさや歩行のしやすさについて見てみるとファスナーの持ち手が大きかったり履き口が広く開口されたり滑り止めが工夫されたりしており、このような靴なら介護者が履かせやすく転倒防止になると思いました。 その他まだまだ機能性の優れた福祉用具がある事、利用者が自立して生活しやすいものが沢山あり驚くことばかりでした。しかし、しやすさばかりにとらわれていると逆に機能の低下につながってしまうのでしょう。そのため、その利用者にあった介護用品と利用者の好む素材やデザイン選びをしなければならないと思いました。 |
 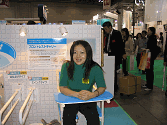  |